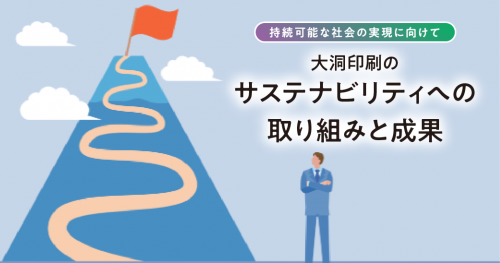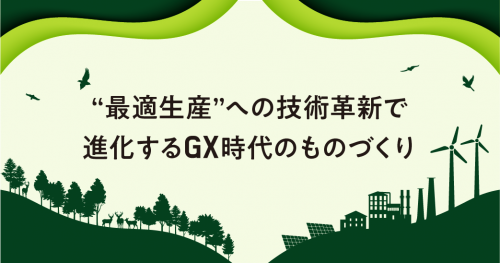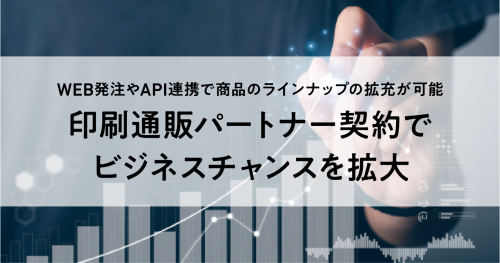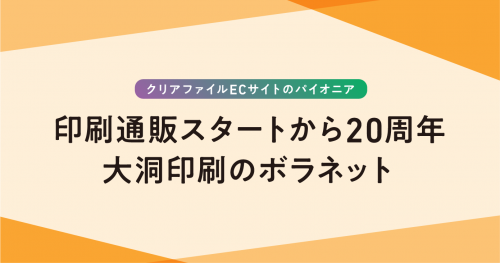私たち大洞印刷もアフターコロナに向けて新たな顧客体験に考えを巡らせています。しかし、これは今に始まったことではありません。当社の経営理念は「CHANGE CHALLENGE CREATIVE」。常に時代の変化と共に、自らを変化させることでお客様のビジネスの成功を追求してきました。その取り組みの一つが以前からご紹介しているDX(デジタルトランスフォーメーション)です。大洞印刷では、お客様が何を求めているかを念頭にDXに取り組み続けています。
DXについては、このコロナ禍で10年速くなったと言われている一方で、昨年末に経済産業省から公開された「DXレポート2(中間取りまとめ)」によると、取り組みができている企業と始められていない企業と二極化しつつあり、それが今後のビジネスを左右する段階に来ているそうです。ターニングポイントとなっている今だからこそ、今回改めて当社のDXについて社内にスポットを当てどう取り組んできたのかをお伝えさせていただきます。
DXへと歩みを進めた背景
印刷業界は斜陽産業と言われるように、2000年頃をピークにその市場規模を年々縮小しています。人口減少、デジタル化、ペーパーレス化などさまざまな要因が絡んでいますが、多様な変化が進む時代に「大量生産時代と変わらない所謂御用聞き営業のような単純なモノ作りビジネスのスタイル」では到底勝ち残っていけない、という危機感が根底にありました。その中で起きた2008年のリーマンショックによる打撃をきっかけに本格的なDXへと乗り出していきました。
デジタル化=DXではない
DXとは、従来のシステムを刷新したりクラウドの活用などオフラインのものをオンラインへと移行したりといったデジタル化を行うことではありません。DXレポート2(中間取りまとめ)の中でも改めて「DXの本質とは、単にレガシーなシステムを刷新する、高度化するといったことにとどまるのではなく、事業環境の変化に迅速に適応する能力を身につけること、そしてその中で企業文化(固定観念)を変革(レガシー企業文化からの脱却)することにあると考えられる。」と提言されています。リモートワークによる働き方改革もそうですが、デジタル技術を用いて変化する環境に対応し、従来の在り方を変えるような「変革」を起こすことがDXと言えるのです。
このようなDXを実現するためには、会社全体で取り組んでいくことが大切です。変革という言葉の通りDXへの道のりの中では、事業内容から業務内容、組織体制など今までの当たり前を大きく変えていくことになるからです。そしてこのような変化をもたらすには、会社の顔である経営層が率先して動く必要があります。トップ自ら指令を出すなど、いかに積極的にDX推進へ関わっていくかが重要になります。
経営層を中心に強い意志のもと始まったDX
当社のDXは経営層を中心に強い意志のもと始まりました。例えばDXへと歩みを進めた当時、当社には担当者が社外に出ると情報を確認する手段が限られすぐに返答ができない、名刺交換や商談が発生してもその情報の詳細は営業担当者しか分からない、見積書や製造手配のためのシステムはあっても情報が分断されておりすぐに確認できないなど、情報が属人的であったりアナログであるが故の課題がありました。
これらを解決し属人化された業務プロセスを変えるため、2008年に導入したSalesforce(※)とGoogleApps(※)というデジタルツールを活用し、まずはアナログなものをデジタルへと移行することを始めました。この導入当時に最初に伝えられたのは、その必要性と利便性です。
弊社では経営層が先陣を切ってDXを推進していたこともあり、社内のDXの成功・継続には社員の実行と浸透をいかに進めていくかが重要なポイントになると考え、大きく2つのことに取り組んでいくことにしたのです。その1つが、なぜ必要なのかを細かくそして根気よく説明し続けること。そしてもう1つが体験することです。
当時の課題
属人化・アナログな情報が多い
・社外では情報把握ができない
・コミュニケーション手段が限られている
・顧客情報や商談情報など属人化した情報が多い
・システムやデータが複数に分かれており業務効率が悪い 等
最初の取り組み
情報の蓄積・共有へ
・Salesforceへの情報入力の徹底 (名刺情報・商談情報・活動情報など)
・GoogleAppsによるファイルの共有化
・紙媒体による管理を禁止
・FAX、見積書などは全てデータとして保管 等
※Salesforce:企業と顧客をつなぐクラウド型顧客管理システム。マーケティング、営業、コマース、サーピスなどすべての部署で顧客一人ひとりの情報を一元的に共有できる。
※GoogleApps:現Google Workspace。Googleが提供するクラウドツール。メールやチャットをはじめとするコミュニケーションツールからドキュメント、スプレッドシート、スライドといったビジネスシーンに役立つ複数のサービスが含まれており、情報共有の基盤として活用することができる。
社内のDXの実行力を高めるために
Salesforceに数年後を見据えデータを蓄積していくことで、経営指標や商談状況などを可視化し数値に基づいたPDCAを速く回したり、GoogleAppsも合わせ情報を共有化することで業務の効率化を実現するなど今後の変革のための基盤を創っていくことができます。そのためには実行力を高める必要があり、何よりも経営層が率先して継続利用することで本気度を示し、体感したからこその利便性を伝えていきました。
しかし、ツールを入れたからといってすぐに業務が改善されるわけではありません。逆にツールを導入したことで、新しいものや変化への抵抗感が生じることもあります。そのため、とにかくデータを入力することが何より最重要業務で評価に繋がることも伝え、半ば強制的に実行するための環境も整えながら、生じる反発には丁寧にその必要性を繰り返し説明していきました。結果、特に業務に直結し体感を得やすい経営企画や営業といった部署から順にデジタルの活用が浸透し、実際にメリットを感じたメンバーが、また周囲にその体験を共有してくれることでその活用度合いはさらに高まっていきました。
また百聞は一見に如かずと言いますが、デジタル化により変化する時代の流れを少しでも社員全員に感じてもらいたいという思いからの取り組みも行っていきました。例えば、その当時はまだ利用者の方が少なかったiPhoneやiPadといった製品の購入費を半額補助するというもの。これは、日常生活においてデジタルに触れてもらう機会を生み出し、体験の場を増やすことが目的でした。体験で得た気付きは何より大きな実行力に繋がります。コロナ禍で月一回の朝礼をZoomによるオンラインに変更したのも、感染予防対策だけでなく、オンライン上でのコミュニケーションが中心になりつつある世の中の変化を社員全員に感じてもらいたいという想いからでした。特に製造に関わるメンバーはコロナ禍でも出社の必要があり、営業やマーケティング、システムといった非対面のコミュニケーションが多い部署と異なり、オンラインでのコミュニケーション機会は少なくなりがちでした。そこで、ウェビナーへの参加を促したり、社内の打ち合わせにもWebミーティングを積極的に取り入れることで、リアルな場に集まらなければできないという固定概念を外したり、世の中の変化やその利便性を伝え続けています。そして、そんな取り組みから蓄積した経験は、ウェビナーやオンライン工場見学会など、社内に留まらないお客さまへの提案のための新たな活動へと繋げています。
お客様の体験をより良いものにするために
印刷業界をはじめ私たちを取り巻く環境は大きく変化してきています。これまで挙げてきた社内の変革はその変化に対応し、最終的にはお客様のビジネスのサポート基盤を強靭にすることに繋がっています。
今後も弊社では、お客様のビジネスを成功へと導くパートナーとなるべくDXという手段も用いながらCHALLENGEを続けて参ります。簡単ではございますが、今回ご紹介した弊社での取り組みの話が、少しでも皆さまの目指すDXの進め方の参考となれば幸いです。
当社のDXの取り組みについて、オンライン面談でお話させていただくことも可能です。
取り組み事例が知りたいなどございましたら、下記より「DXへの取り組みについての話を聞いてみたい」とオンライン面談をお申込みください。
![]()