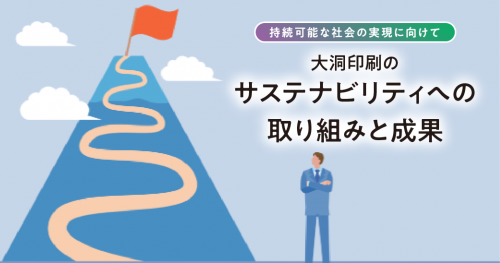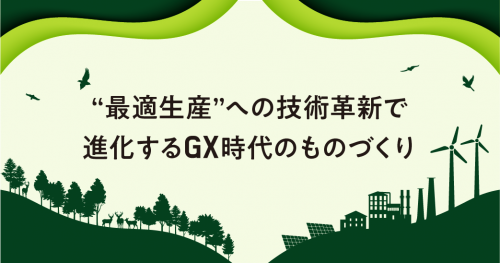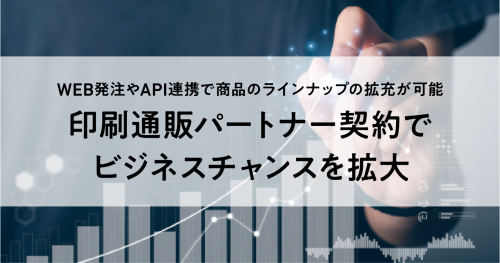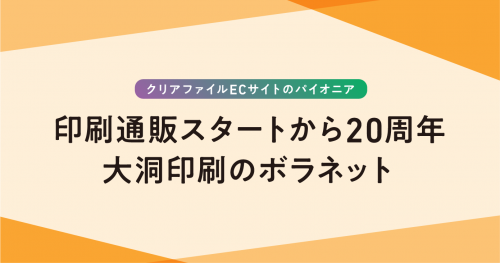印刷業界と「つくる責任つかう責任」
製造業である印刷業界は、多種多様な業種と関わりながら、チラシや名刺、雑誌、パッケージ、ノベルティなど、クライアントの要望に応じた商品の製造を請け負っています。そのクライアントの多くがSDGsへの取り組みを強化している今、印刷業界もまた、取り組みを加速させています。
特に環境への取り組みは、SDGs以前から、その重要性が示唆されていました。印刷物の製造は環境負荷と関わる面が多いとされているからです。例えば、よく話題として取り上げられているものとして、森林伐採やCO2の排出、印刷時の有害物質、リサイクル促進があります。この4点について、少し解説していきます。
森林伐採
印刷では紙資源を多く使用します。そのため、その紙製造にあたり発生する森林伐採についての問題がよく取り上げられます。ですが、ここで注意したいのは、森林伐採=環境に悪いわけではないことです。適切な管理下であれば、逆に健康な自然を維持する大切な役割を担っています。ここで問題視されているのは、過剰な伐採にあたるものです。そのため、製紙会社では、森林の管理や伐採が、環境や地域社会に配慮されているかどうか第三者機関で認証されているFSC認証紙の提供などに取り組んでいます。
他にも、印刷物の素材という観点でいけば、リサイクル用紙や、木々に加え、水や石油系資源の削減に繋がる新素材LIMEX、紙以外のプラスチック素材などではバイオマスプラスチックの開発など、さらなる持続可能な素材の開発なども進められています。
CO2の排出
印刷業界では、資材の仕入れから印刷物の製造、そして発送に至るまで、多くの工程でCO2が排出されています。そのため、この排出量を少しでも抑えるべく、設備の省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用を促進したり、時にカーボンオフセットも活用しながら、CO2の削減に取り組んでいます。
またそれ以外にも、適切な量を作ることでCO2排出を抑えることができますので、生産の効率化や、適量で製造できる仕組み化、そしてクライアントにも適切な数量でのご発注を提案したりと、さまざまな取り組みが進められています。
印刷時の有害物質
印刷インキをはじめ、印刷に使用する資材の中には揮発性有機化合物(VOC)が発生するものもあります。この中には、大気汚染にも繋がる石油系溶剤が含まれていることもあり、この有害物質の発生をいかに減らせるかも課題としてよく取り上げられています。
そのため、例えばVOCフリーインキなど、そもそも有害物質が含まれないものを活用したり、使用する場合には、VOC警報器やVOC処理装置を導入するなど、環境はもちろん、製造者の健康を守るための取り組みが行われています。
リサイクル促進
リサイクルは、限りある資源を有効に活用するための手段として、消費者の生活にも浸透している非常に重要な取り組みです。印刷会社内でも、廃棄物の分別、リサイクルの取り組みは積極的に進められています。
しかし、商品となった場合にはさらに一歩踏み込んで考えていく必要があります。それは印刷物の種類によってリサイクルの品質が変わってくるからです。例えば紙のリサイクルでは、当然紙以外の異物が混入すればするほど、そのリサイクルは困難になります。そのため、廃棄のサイクルまで考慮したいと考えるクライアントには、紙=リサイクルが可能ではなく、より適切な仕様での提案を行うといった取り組みも進められています。目的により適切な素材や手法は異なってきますので、要望に応えるための提案力はこれからもますます必要になってくると考えられます。
持続可能な生産形態を目指す
SDGs目標12の大きな目標は、今後も持続可能な生産と消費の実現です。環境への取り組みをいくつか挙げてきましたが、今後はさらなる取り組みが必要となってきます。
例えば、これまでの生産形態のそもそもの見直しです。これまでの印刷業界も、大量生産・大量消費の時代を経て今に至ります。その中で、発注者も製造者側も、印刷物は不足するよりは多めに作る方が良いと、在庫を持つことを前提とした運用と考えが根付いている部分がありました。オフセット印刷の場合、大量に印刷すればするほど単価が下がります。経済効率を優先し、まとめて安価に作っておいて、コストを削減し安く販売できれば良いという消費形態がベースにあったからです。

在庫を前提にしていても、それが適正な数量であれば問題ではありません。しかし、従来この在庫は、過剰在庫であることがほとんどでした。情報が更新された時に、過剰分が廃棄されるなど、せっかく作り出したものが、本来の用途に使われずに終わってしまっていたのです。
極端ですが、これは、ゴミの生産を手伝ってしまったとも言えるのではないでしょうか。印刷会社は、印刷機の回転数を上げ、量を納めることで利益は出るかもしれません。しかし、自社の利益だけを追い求めてこのような生産を続けることは、果たして未来の持続性に繋がることなのでしょうか。今後は、多くの業界同様、さらなる根本的な製造の仕組みからの見直しも必要になってくると予想されます。
注目ポイント1 デジタル印刷機の活用
最近では、そんな無駄が少ない印刷方式としてデジタル印刷が注目されています。デジタル印刷には、インキ自体が環境に優しく、版が不要で、必要な量だけ作ることができるというメリットがあります。多品種小ロット化が進む今、その需要に応じた印刷物が作れる印刷手法として活用されています。
しかし、デジタル印刷を単純に小ロット化に対応するものとして活用してしまうと、印刷通販の台頭により価格競争も進む今、かける労力は大量生産の時と変わらないのに、手間が増え、利益が出ないという状態になってしまいます。人も企業も疲弊してしまうビジネスモデルは、それこそ持続することはできません。
今後も持続可能なビジネスを生み出すためには、そのビジネスの在り方を見つめ直し、仕組みづくりから取り組むことも重要になってきます。
注目ポイント2 自動化
製造の仕組みの見直しにあたり、もう一つ注目されているのが、自動化による生産効率化です。プリプレスでのデータチェックや製版作業、さらには印刷から後加工の工程まで自動化することで、生産効率を最大化することを目指しています。これにより、製造における全工程で使用するエネルギーが最適化され、印刷時の廃棄物が減少すれば、CO2の排出量の減少などにも繋がっていきます。
また、もう一つの狙いは、労働力不足の解消です。印刷物出荷量の減少とともに、その生産工場も徐々に減少しつつありますが、このまま工場も人も減少した場合、従来の人の力だけで市場の供給を賄うのは難しくなり、労働環境も悪化してしまうのではないかと言われています。自然環境以外にも、人権問題などへの配慮も企業選定の上で重要な項目となっている今、それを防ぐための自動化も、避けては通れない取り組みの一つではないでしょうか。
しかし、さらに考えたいのは、自動化の先です。この自動化が進み、生産効率が上がれば、従来は実現できなかった付加価値のある印刷物がコストを抑えて、新たな市場に提供できる可能性も出てきます。クライアントの要望に合わせた、最適な価格や納期、仕様などで提案できるようになれば、より良い消費形態の実現にも貢献していくことができるのではないでしょうか。
さて今回、SDGs目標12を考えるにあたり、実際に商品を作る製造の現場には、どのような取り組みがあり、さらには、どんな想いで商品作りにあたっているのかを、当社本社工場のメンバーにインタビューしました。皆様のビジネスに、何か一つでも参考となる点がありましたら幸いです。