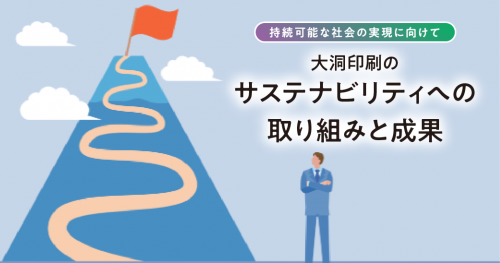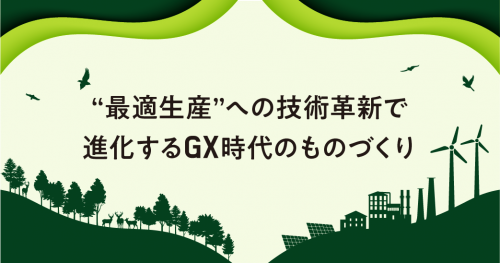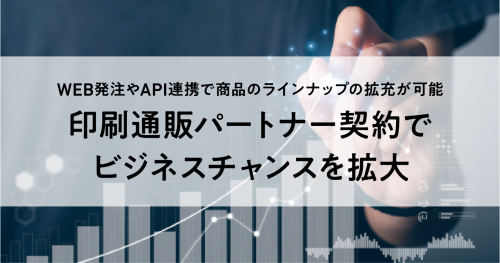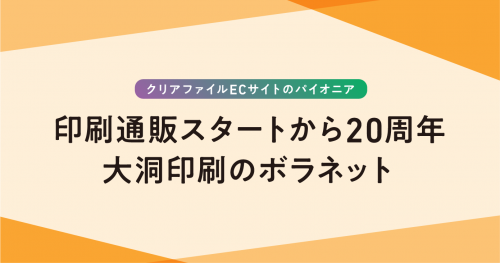なぜDXは注目されているのか?
みなさん、「2025年の崖」という言葉をお聞きになったことはありますか?経済産業省が2018年に発表した「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開」にある言葉です。具体的には、「2025年の崖」として下記の警笛を鳴らしています。
多くの経営者が、将来の成長、競争力強化のために、新たなデジタル技術を活用して新たなビジネス・モデルを創出・柔軟に改変するデジタル・トランスフォーメーション (=DX)の必要性について理解しているが・・・ ・ 既存システムが、事業部門ごとに構築されて、全社横断的なデータ活用ができなかったり、過剰なカスタマイズがなされているなどにより、複雑化・ブラックボックス化。 ・ 経営者がDXを望んでも、データ活用のために上記のような既存システムの問題を解決し、そのためには業務自体の見直しも求められる中(=経営改革そのもの)、 現場サイドの抵抗も大きく、いかにこれを実行するかが課題となっている。 → この課題を克服できない場合、DXが実現できないのみでなく、2025年以降、最大12兆円/年(現在の約3倍)の経済損失が生じる可能性(2025年の崖)。
そして、これを回避するために、下記のDX実現シナリオを提言しています。
2025年までの間に、複雑化・ブラックボックス化した既存システムについて、廃棄や塩漬けにするものなどを仕分けしながら、必要 なものについて刷新しつつ、DXを実現することにより、2030年実質GDP130兆円超の押上げを実現。
政府機関による民間企業への言及は異例のケースです。ターニングポイントである2025年は目の前です。そして、今回のコロナショックにより、ターニングポイントは前倒しになる可能性もあります。
DXの事例
ここからは2つほどDXの事例をお伝えします。
① Amazon(amazon.co.jp)
Amazonといえば、前号でもお伝えした通り、世界最大級のマーケットプレイス型のネットショップ。売り手に販売の場を提供したり、取引情報を2次活用した広告の仕組みを活用し拡大。それ以外にも、音楽や動画などのコンテンツ配信サービスの提供、Amazon Web Services(AWS)と呼ばれるクラウドコンピューティングサービス事業などを展開しています。
多岐に渡った事業を展開しているAmazonですが、「書籍を中心に扱うインターネット書店」から創業した企業です。創業当時はWindows95の発売前で、「インターネットを経由して本を売る」というビジネスモデル自体が成立していない、人々に定着していない時代でした。どうすれば顧客からリアル店舗以上に選んでもらえるかなど、ビジネスモデル自体が不透明であるという課題がありました。そこでAmazonはユーザーファーストを徹底させ、カスタマーレビュー機能やレコメンデーション機能、使いやすいUI設計(1クリックですぐに購入できるボタン、面倒な情報入力の手間軽減)などを次々と行いました。そして、「インターネットで本を販売・購入する」というビジネスモデルを確立させました。ここからさらに「最高の顧客体験」をテーマに前述した多くのサービスを実践し、爆発的にシェアを拡大していきました。
②株式会社メルカリ(mercari.com/jp/)
みなさんご存知のフリマアプリ「メルカリ」を提供している企業です。
メルカリ登場以前は、インターネットオークションが主流でした。インターネットオークションといえば、パソコンで行う、出品者も購入者も実名で行うことが前提のサービスがほとんどでした。個人間で取引をするのにも、取引のハードルは高いサービスとなっていました。そこをデジタル技術により、スマホで気軽に出品でき、匿名で配送できるというサービスを作り上げました。これによりハードルの高かった個人間での中古商品の売買が簡単になり、新たなビジネスモデルとして広く定着をさせました。
近年では「メルペイ」という決済サービスもスタートし、既存のサービス以外にも枠を広げていっています。
これらに共通するのが「顧客中心主義」という考えです。ユーザーの利便性を第一に考え、デジタルを使った新たな体験をサービスとして提供しています。モノを開発するという考えから、体験などのコトを開発し収益を上げる、この考えが今後重要になってくるのではないかと思います。
弊社のDXの取り組みについてはこちらからご参照ください。